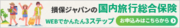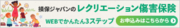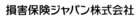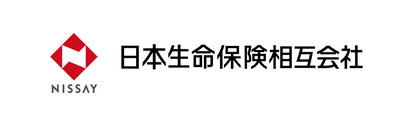【認知症】認知症に関わる法的諸問題について
2017/01/30認知症を患うと、様々な法的な問題と直面するようになります。
諸問題について、大まかですが整理します。
意図しない損害を被らせてしまうことについての法的問題
認知症を患えば、自分の行為の責任を認識する能力を欠く状態(責任無能力者)となり、損害賠償責任を負いません。(民法713条)
認知症患者の保護のためです。同時に取引安全の確保、被害者の保護も必要になってきます。
そこで、監督義務者の責任が問われます。認知症の人を監督する人(成年後見人、配偶者や同居人等)がその責任を負うことになります。(民法714条)
監督責任の重さは、事例よって判断します。判例では監督義務者としての義務が否定された事例もあります。
■認知症列車事故
2007年、認知症患者が電車に接触し、同居の妻・別居の息子に対して監督責任者の責任が問われました。2016年3月1日の最高裁判決では、監督義務を認めませんでしたが、生活状況や介護の実態などを総合的に考慮したうえで家族が監督義務者に準じる立場としての責任を負うか個別に判断すべき、との見解が示されました。
今後、認知症患者の家族が監督義務者として損害賠償請求を受けるケースがますます増えそうです。
■個人賠償責任保険の改定
この裁判を契機に、一部保険会社では個人賠償責任保険の被保険者の範囲を広げ、監督義務者や親権者を被保険者に追加するなどの改定を行っています。なお、監督義務者は別生計、別居であってもかまいません。
個人賠償責任保険は、他人の物を壊したり、他人にケガをさせてしまったりした時に補償される保険です。
財産管理についての法的問題
認知症を患うと判断能力が低下してきます。
意思能力が無い(意思無能力者)がした法律行為(売買契約、賃貸契約、遺言、生前贈与)は無効になります。
ただ、認知症だからといって意思能力が無いとは限りません。程度に応じた対応が必要になります。
遺言の無効確認の訴訟が多く見受けられます。生命保険契約や不動産売買についても、もめる種です。
■法律行為の有効性の判断要素
法律行為の有効性の判断要素として、まず医学的な観点が考慮されます。
●医師の診断書やカルテ。
●認知症の種類(アルツハイマー型か脳血管型か)によって症状が異なる点。
●改定長谷川式簡易知能評価スケールやミニ・メンタル・ステート法などの検査結果
(参考)改定長谷川式簡易知能評価スケールを試してみよう →https://info.ninchisho.net/check
法律行為を行った時の経緯、動機、人間関係、また法律行為の複雑さなどを総合的に判断しています。
●遺言が複雑で認知症患者ではムリだと判断されたケース。
●逆に遺言内容が単純で(家業を長男にあげる等)認められたケース。
●不仲の三女に、全財産をあげる旨の遺言に変更していたが、合理性がないとして無効とされたケース。
●認知症患者の返事が簡単(「ハイ」しか言わない)で、法律行為ができないと判断されたケース。
将来に起こるであろう紛争を予防する対策もとっておきましょう。
●カレンダーにメモしておく。日記を書いておく。
●法律行為を行う際の録音、録画。
●書類は確定日付をとるなど
判断能力がある早期のうちに、具体的な財産管理方法を検討します。
早いうちに、財産管理契約、任意後見契約、遺言、生前贈与、信託を行うようにしましょう。
判断能力がない状態になれば、法定後見手続きを検討します。この場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
家族の者がなることはできず、弁護士が担当します。思うような財産管理にはならないかもしれません。
これらを行う際には弁護士に相談してみたらよいでしょう。
自動車事故の場合の法的問題
認知症の方が自動車事を起こした場合は、前述のとおり不法行為による損害賠償義務は負いません(民法713条)
しかし、自動車損害賠償補償法(自賠法)による運行供用者責任(自賠法3条)は負います。
運行供用者とは、車の所有者など、車の支配する者、運転によって利益を得る者をいいます。
被害者は自賠責保険によって補償はされます。
前述のように、監督義務者に当たる者に賠償責任は発生します(民法714条)
道路交通法に関する法的問題
認知症が原因とされる交通事故の増加により、道路交通法が改正されました。
3月12日には改正道路交通法が施行されます。
新設!
3年に1度の免許更新時の臨時機能検査が、一定の違反行為があれば、3年を待たずに受けることになります。
その臨時機能検査の結果が悪くなっている場合、臨時高齢者講習を受けなければなりません。
実車指導、個別指導、それぞれ1時間、計2時間となっています。
機能検査で認知症のおそれがあると判定された時は、医師の診断を受けることになります。
診断の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取り消しの対象となります。
お気軽にご相談ください
株式会社 アワーサポート 
TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670
〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34
営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)
上記以外の時間も連絡可