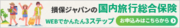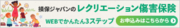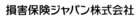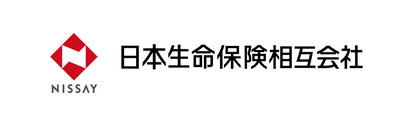第12番 焼山寺
2016/04/17
焼山寺の麓には『杖杉庵(じょうしんあん)』があります。お遍路の第一人者・衛門三郎が弘法大師と出会い、力尽きた場所です。

金持ちで意地汚くて近所の評判も悪い衛門三郎は、家の前に現れた托鉢僧(正体は弘法大師)をホウキで叩き、鉢も叩き割ってしまいます。するとその後、8人いた衛門三郎の子どもたちが次々と変死します。弘法大師を怒らせると後が怖いのです!

すっかり憔悴した衛門三郎は弘法大師に謝るためお遍路に出るのでした。20周しても会えない衛門三郎に名案が浮かびます。逆にまわれば、会えるのでは⁉ 切幡寺から逆にまわった衛門三郎は、焼山寺の麓で大師と出会うのでした。

すっかり反省した衛門三郎の情けない表情。「もう一度生まれ変わって百姓民のために功徳をつみたい」と願い、衛門三郎は息を引き取り、そしてまた、生まれ変わるのでした。続きは51番札所石手寺で。

『逆打ち』した衛門三郎が大師と会ったのが『うるう年』だったことから、『うるう年』の今年(2016年)は『逆打ち』すると、ご利益3倍だそうです。

大師が墓標として衛門三郎の杖を立てると、杖から芽が出て大きな杉が育ちました。しかし、享保年間に落雷で焼失。この大杉は2代目です。

神山名物の梅干しも忘れてはいけません。

狭い山道を車で上がるとすぐです。焼山寺に着きました!

灯篭が並ぶ参道を歩いていきます。けっこうな長さです。

『十三仏』を見ながら参道を歩いていきます。

弘法大師の大蛇倒しを手助けした『虚空蔵菩薩』です。

石段の上に仁王門があります。

仁王門をくぐると、樹齢100年を超える立派な杉。壮観です。

ふたたび石段を登って本堂に着きます。

奥が本堂、手前が大師堂。

稚児像が、隠れてこっちを見ています。

とても、かわいらしい。

手洗い場にもいました。細かな演出で微笑ましいです。

山の中のふくろう。

焼山寺がよく似合う、虎。

意味不明ですが、牛。

そして、『三面大黒天』。中央が大黒天、右面が毘沙門天、左面が弁財天。日本でここだけの貴重なものです。

奥の院への案内がないので、納経所で聞きました。

奥の院へ行ってみます!

歩き始めてすぐに後悔しました。上り坂が思ったよりきつい。

むかしむかし、天変地異をもたらす大蛇に悩まされていたところ、村人たちのヒーロー、弘法大師様が現れました!
山を火の海にする大蛇を、虚空蔵菩薩のご加護のもと岩窟に封じ込めました。

これが大蛇封じ込めの岩です。

それからさらに登り道が続きます。

残り300mですが、まだまだ長く感じます。

こんな祠がありました。納札が置かれています。納札は、名刺のようなもので、住所や氏名を記入して本堂や大師堂に納めたり、お接待を受けたお礼にお返したりします。

納札は、巡礼の回数によって色が違います。4回までは白札。7回までが青札。24回までが赤札。49回までが銀札。ここからは別注で、99回までの金札。100回以上が錦です。金色の納札は初めて見ました。

上へ上へと登っていきます。山道に横たわる倒木が、大蛇のようです。

足場がだんだんと小さくなってきます。ゴールが近いことを示しています。

ようやく着きました。奥の院『蔵王権現堂』です。

飛鳥時代に役行者(えんのぎょうじゃ)が山を開いて、蔵王権現を祀ったのが焼山寺のはじまりでとされます。

素晴らしい眺めです。しばしの休息。

下山して帰らなければなりません。面倒くさいことこの上なし。

帰りは下り道のぶん、早かったです。心にも余裕ができました。

こんな分厚い『サルノコシカケ』を見つけました。

煎じたら、がん予防にも良いだとか。

以前、日が暮れようとしているある日のこと。車のキーを焼山寺のどこかで失くした、と必死で探している人を見ました。
こんな山奥で忘れ物をすると大変です。
お気軽にご相談ください
株式会社 アワーサポート 
TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670
〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34
営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)
上記以外の時間も連絡可